歴史解説 えっ!これが京都? 織田信長も見た戦国時代の京都をCGで完全再現 当時の京都は想像と全く違う、意外な姿だった!
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 5 ก.พ. 2025
- 前回と前々回の2回にわたって、戦国時代、1570年頃の京都の町の様子をCGで紹介してきました。前回までは、当時の京都の中心地が、堀で囲まれた、上京と下京の2つに分かれて存在していたことを紹介しました、今回は上京と下京の周辺にあった、社寺と集落を紹介すると共に、改めて上京と下京についても触れてみようと思います。
上京と下京は、単に位置が違うだけの同じような町なのではなく、構成員の違いによる性格の違いもありました。単純に割り切れませんが、大きく見ると上京は御所を中心に公家、武士、富裕層が住む町政治的・文化的な側面が、下京は、商業地区であり、祇園祭に代表される民衆・経済の町と言えるかもしれません。こうした違いは時代を超えて、今でも息づいているようです。両者は戦国時代だけでも何度も火災にあっています。しかし、両方が一度にそのほとんどを焼失してしまうことはなかったようで、その都度再建されてきました。
こうして復興を遂げてきた京都の町が次に大きく変わるのは、秀吉による京都の大改造によってです。それはもう目前まで迫ってきていました。
【参考文献】
京都時代MAP 安土桃山編 光村推古書院 2016
戦国時代の京都を歩く 河内将芳 吉川弘文館 2014
日本都市史 高橋康夫・吉田伸之・宮本雅明・伊藤毅編 東京大学出版会 1993
京都歴史アトラス 足利健亮編 大日本印刷株式会社 1994
寺社勢力の中世-無縁・有縁・移民 伊藤正敏 ちくま新書 2008
【関連動画】
えっ! これが京都? 織田信長も見た戦国時代の京都の町【CGで再現】中編 下京編 1570年頃の京都は想像と全く違う、意外な姿だった!
• えっ! これが京都? 織田信長も見た戦国時代...
【えっ! これが京都? 織田信長も見た戦国時代の京都の町をCGで再現】前編 上京編 1570年頃の京都は想像と全く違う、意外な姿だった!
• 【えっ! これが京都? 織田信長も見た戦国時...
【聚楽第】秀吉が京都に築いた巨大城郭を3DCGで再現
• 【聚楽第】秀吉が京都に築いた巨大城郭を3DC...
【躑躅ヶ崎館】戦国最強の武将・武田信玄の居城!躑躅ヶ崎館を3DCGで再現
• 【躑躅ヶ崎館】戦国最強の武将・武田信玄の居城...
【3DCGで蘇る幻の二条城!】信長が義昭のために建てた城を発掘調査&古文書で徹底解明
• 【3DCGで蘇る幻の二条城!】信長が義昭のた...
【小谷城】甦る戦国の巨大山城 浅井長政が織田信長と攻防を繰り広げた城
• 【小谷城】甦る戦国の巨大山城 浅井長政が織田...
【大坂城】ここまでわかった! 豊臣秀吉の大坂城の姿
• 【大坂城】ここまでわかった! 豊臣秀吉の大坂城の姿
【新説 関ヶ原の戦い】徳川家康が石田三成らの西軍を関ヶ原で破ったとする定説は覆されるのか?
• 【新説 関ヶ原の戦い】徳川家康が石田三成らの...
【小田原城】戦国時代最大級 北条氏五代の巨大城郭 秀吉も力攻めでは落とせなかった城
• 【小田原城】戦国時代最大級 北条氏五代の巨大...
【安土城】信長の集大成の城 当時の地形をCGで復元
• 【安土城】信長の集大成の城 当時の地形をC...
【武田氏滅亡】織田信長・徳川家康に追い詰められた武田勝頼、天目山手前の田野で自決し、武田氏滅亡す。 信長・家康に追い詰められた勝頼、天目山で自決し、武田氏滅亡す。
• 【武田氏滅亡】織田信長・徳川家康に追い詰めら...
【長篠城と長篠の戦い】武田軍vs 織田・徳川連合軍 最新研究によって明らかになった長篠の戦い
• 【長篠城と長篠の戦い】武田軍vs 織田・徳川...
#京都 #戦国時代 #織田信長
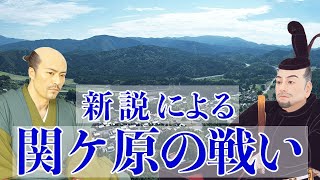








今回も素晴らしい内容でした。唯一無二のチャンネルだと思います。
配信を楽しみにしています。
ありがとうございます!素敵なコメントをいただき、嬉しいですが、恥ずかしいというか、恐縮です。もっと調査して、CGのレベルも上げて、少しでもいただいたお言葉にふさわしいものになるよう、頑張ります。今年もよろしくお願いします。
いや、本当に面白い。
脳内想像をCGで補完する労力は相当に大変だと思うので、これを視聴できることにただ感謝。13:00くらいからは特に見ものかな。
明けましておめでとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけると有難いです。年末にアップするつもりだったのですが、予想以上に苦戦し、結局今日まで休みなしで作ったのですが、とても間に合わず、諦めてアップしてしまいました(笑)。今年もよろしくお願いします。
大変楽しみにしておりました! お疲れ様でした!
ありがとうございます。楽しんでいただけたら幸いです。今年もよろしくお願いします。
TH-camを見だしてから十年以上、最高の動画です。歴史ドラマの楽しみ方がかわります。
ありがとうございます。過分なお言葉をいただき、恐縮です。不完全な所はたくさんありますが、少しずつ修正して行こうと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
大変勉強になりました。イメージとしては「こんなもんだろうなぁ」とは思っていましたが実際にCGで見るとより一層イメージが固まりました。次回作楽しみに待ってます。
ありがとうございます!CGで見ると、合っているかどうかは別ですが、それなりに作りこんであるので、クリアな印象になりますよね。次の動画も楽しんでいただけるようがんばりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
京都の変遷がとてもわかりやすく素晴らしいです。
脳内で各時代の京都をデジタル散歩できちゃうぐらい参考になる動画です。
ありがとうございます! そう言っていただけると嬉しいです。今年もよろしくお願いします。
大阪人です。
京都は何回行っても道が分かりません!
CGで再現されても記憶にございません🙏
でも、楽しいです😉
この動画を記憶にまた京都に行きたいと思います!
ご視聴いただき、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです!記憶に残る旅になるといいですね!
今回も凄く楽しみにしておりました。
ここまで作り込まれることを毎回
感動しております。🙇♂️
現在の様子と比較して、当時の京都を想像して楽しんでおります。
これからも、このような動画を
楽しみにしております。
毎回、ほんとうに有難うございましたとお疲れ様でした。
いつもご視聴ありがとうございます。また、このような素晴らしいコメントをいただき、恐縮です。重ねてお礼申し上げます。これかからも楽しんでいただける動画を作っていこうと思いますので、今年もよろしくお願いします。
私の通っていた上京区の小学校は、足利義満から拝領したとされる能楽の観世家の邸宅があった場所で、ちょうど飛鳥井家(今の白峯神宮)の西に当たります。観世家の邸内社だった「観世稲荷」が校内にあり、名水「観世水」が出る井戸があったのを覚えています。この観世水は近くの菓子司鶴屋吉信の銘菓の由来になっています。
貴重な情報ありがとうございます。地元にお住まいだったからこその情報ですね。飛鳥井家の名称は地名として残っているんですね。
!ご近所さん発見
今日一度見ましたが、改めて後日見直します。素晴らしいと思います。
ありがとうございます! また見ていただけると嬉しいです。今年もよろしくお願いします。
いやあ、勉強になりました!Google Mapと繰り返し照らし合わせながら拝見していると、位置関係が一層よく理解できました。大変な労作と感じました。引き続きよろしくお願い致します。
こちらこそご視聴いただき、ありがとうございます。なるほど、そういう使い方もあるんですね! 面白いですね。少しでも参考になれば幸いです。これからもよろしくお願いします。
私の生まれた都は500年を超えて甦りました😊私の祖先は公家から家紋を賜りました😊
往時をしのびました😊
いつもご視聴ありがとうございます。過分なお言葉ありがとうございます。表現しつくしたとするにはかなり不十分ですが、少しでもそのように感じていただけたとすればよかったです。今年もよろしくお願いします。
新年からご苦労様でございます🙇🏻
明けましておめでとうございます。暖かいお言葉ありがとうございます。私は明日から正月です(笑)。少しばかり休みます。今年もよろしくお願いします。
@ 🎍あけおめです🎍ゆっくり美味しい物食べて英気を養って下さい😊今年も動画楽しみにしてます👍
限られた資料での作成、ご苦労様です!
明けましておめでとうございます。ありがとうございます。おっしゃる通りです。本当はもっとたくさん集落もあると思いますし、農村、農家の表現もしたかったのですが、どこにどれくらいあったのか、私が調べきれなかった部分もありますし、作る余裕もありませんでした。また、社寺は多すぎて途中であきらめました(笑)。今年もよろしくお願いします。
「祇園感神院」の鴨川西岸の四条通沿いの大鳥居と西楼門前の大鳥居は初めて知りましたが?
本来正門である南楼門前の石鳥居と、門前町の下河原通が全く描かれていないのが気になりました🧐
細かいところですが、古来より「感神院」は南楼門が正門で、江戸時代には祇園町通(四条通)に比べ廃れていたかも知れませんが、祇園の花街と共に通が発展するのは秀吉時代以降、なので下河原町通の方に町家が多く在ったはずだと思います。
ご指摘ありがとうございます。祇園大鳥居は、歴博本洛中洛外図屛風には描かれています。この表現は中世の祇園社の絵図を見ながら作りましたが、どこまで正確なものなのか、また絵図に描かれているものでも、表現がよくわからないものについては省略していますので、そんなに正確なものではないです。東山の市街地がどの程度広がっていたのか、また大和街道・鳥羽作道も本当にこれで正しかったのか、最後まで悩みました。未だわからないことばかりですので、もしお気づきの点等ございましたら、是非ご教示いただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。
早速誠実なご返信、ありがとうございます。
ご承知でしょうが、描かれたのは江戸中期ですが、平安〜安土桃山時代の京都の地図「皇州餘撰部 中古京師内外地圖」によれば、感神院(現八坂神社)の西楼門に至る祇園町通(現四条通)に比べ、正門の南楼門の表参道の下河原通は、「百度大路」や「祇園大路」と呼ばれていたようですね。
多分当時多くのの参拝者は四条通からでは無く、先ずは五条橋を渡り松原通の途中から下河原の表参道(祇園大路)を上って「感神院」を参拝し、戻って五条坂を登って清水寺へ向かっていたのかも知れませんね。
現在の松原橋や松原通も、五条橋から清水寺へ繋がる参道として大きく描かれています。
また桃山期以降に廃寺になり、その後跡地に高台寺が建った「雲居寺」も描かれていますね。
@@katsuohnojp2003 こちらこそ貴重な情報をありがとうございます。中古京師内外地圖は存じておりますが、申し訳ないのですが、江戸時代中期のものであること、時間的に手が回らなかったことから、今回の3Dモデルを作るにあたってはほとんど利用していません。百度大路、とても参考になりました。次回の動画までに追加してみようと思います。「雲居寺」に限らず、抜けているところだらけです。お恥ずかしい限りです。あと、法住寺殿跡やそこにあったであろう池、六勝寺の一帯がこの時期どうなっていたのかも気になったのですが、時間切れで出来ませんでした。またお気づきの点がございましたら、いつでもコメントください。今後ともよろしくお願いいたします。
室町末期~戦国後期の『洛中洛外図』に描かれた都のCG化、楽しく大変興味深く拝見しました
4:05 五條橋(現 松原橋)中洲の様子が再現されており、晴明の伝承がある法城寺や大黒堂といった、現存しない寺院や地形の再現は非常に価値がありますね。
左岸側の清水坂は、中世には下級陰陽師を含む雑芸民や、清水寺の隷属民(犬神人や弦売僧)といった、当時卑賤視のされていた職能民が集住した地域であり、大黒堂を管理する清水寺成就院が『普請作事』など勧進職(勧進僧、彼らも下級身分的な半僧半俗)の統括的役割を担っていたとのことで、投稿主様の説明どおりやなぁと深く理解できた次第です
ご視聴いただき、また格別のお言葉をいただき、ありがとうございます。最後に子指摘いただいた点、私よりもはるかにお詳しいですね。清水寺に至る六条坊門小路をはじめ、その周辺の町が当時どのようになっていたのか、色々調べてみたのですが、上京と下京のようには明確に分かる資料を見つけることが出来ませんでした(勿論上京と下京も完全ではないですが)。多分もっとにぎやかだったと思うんですが、これだけに留めました。aiai4445さん、もし何か資料をご存じでしたらご教示ください。今後ともよろしくお願いいたします。
長文コメントにも係わらず、懇切なるお返事を頂き却って恐縮です
手元にある文献ですみませんが、下記のとおりになります
① 日本の歴史を読み直す(筑摩書房)網野善彦 第三章『畏怖と賎視』92-97頁、101-104頁
② 京都 歴史と文化2【宗教・民衆】(平凡社)第二部:民衆の都市 (川嶋将生)201-204頁
③ 日本の歴史10 下剋上の時代(中公文庫)永原慶二 237-238頁、247-249頁
また、清水寺成就院と勧進僧の関わりについては、下記wikipedia(『願阿弥』の記事)を参照しました
ja.m.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E9%98%BF%E5%BC%A5
以上、またしても長文となり重ねて失礼いたしました
これは、秀逸な動画です
ご視聴いただき、ありがとうございます。引き続き続編を作っていきますので、よろしくお願いします。
勉強になります、新創社の地図を参考にされたのでしょうか?今の地図と重ねて見られる面白い本です
こちらこそありがとうございます。そうですね。ずっとこれをベースに使っています。とても重宝しているんですが、昨日『重ね地図で読み解く京都千年の歴史』(宝島社)が届いたので見てみたら、新創社のとはまたかなり違って、もっとたくさん家があるようでしたので、諦めました(笑)。あくまでも中心部分が上京と下京に分かれて堀を巡らせていたということで、周辺にはこうしたまとまりはなくとも、ここで表現したものよりもかなり多くの集落があったのだと思います。機会があれば再度挑戦してみようと思います。
室町無頼を鑑賞前にイメージが湧いてきてワクワクしました。ありがとうございます。
こうして見ると、二条城や東西本願寺などの江戸時代入ってからの建造物が室町後期の洛中から外れたところにできてきたのが面白いですね。
秀吉の御土居楽しみにしてます!
コメントありがとうございます。3Dて視覚化するとわかりやすいですよね。期待に添えるよう、頑張ります。今年もよろしくお願いします。
大変勉強になりました🙇
ご視聴いただき、ありがとうございます。少しでも参考になれば嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。
上京に近衛邸が、下京に二条邸があったということが、室町時代後期に将軍家の争いが摂関家をも巻き込んで展開されていったことを暗示するようにも見えますね…
両家は後に関白相論でも抜き差しならぬ対立関係になりましたし
ご教示ありがとうございます。皆さんの方が詳しいですね。今年もよろしくお願いします。
素晴らしい動画ですね😄 CGはどのようなソフトを使っているのでしょう?? 私も作ってみたいww
いつもありがとうございます。恐縮です。ソフトはblenderというソフトです。無料でダウンロードできますし、チュートリアル動画やサイトはネット上に山ほど出ていますので、とっつきやすいと思いますよ。頑張ってください!
事件の解決に尽力した捜査官に感謝します🙏
すいません、意味深過ぎてよくわかりませんが、捜査官って私の事ですか?
素晴らしい、パチパチ👏です。京都の人間としては興味津々で見ました。
特に、今住んでいる場所が嵯峨野なので、今回、天竜寺、釈迦堂、大覚寺あたりは特に興味深かかったです。また説明は無かったですが、京都と嵐山の中間地点として帷子ノ辻も再現されていました。
出来れば、今の地図と重ねていただくと、住んでいる人間としては、より距離感が判り易くなります。特に上京、下京と二条城の距離感は掴みやすくなります。
ところで、この当時、どの程度の人口だったのでしょうか?
次回、御土居とのことで、北野神社の御土居跡で遊んだ事もあり、興味津々です。建築当時の御土居の雰囲気を知りたいと思います。
長文失礼しました。
明けましておめでとうございます。ありがとうございます。嵯峨一帯の部分の製作中は、常にkoshihosokawa7849さんの前回のコメントを意識してました(笑)。ただ、やはり京都全体をこれだけの短期間で作るのはちょっと無理がありました。大分いい加減です(笑)。今年もよろしくお願いします。
法堂は(はっとう)と読みます。
すいません、気をつけます。ありがとうございました。
戦国京都、完成おめでとうございます⛩何度焼かれても立派な街だな
ありがとうございます。まだ全然十分ではないのですが、とりあえず分かる範囲でという事でアップしました。また順次情報を追加していこうと思います。
当時の何にもない京都の中にいろんなお寺や神社を配置してみると
いかに神社仏閣が多く建立しているかがよくわかりますね。
本当に多いですよね。郊外にはもっとあるんですが、途中であきらめました。また少しずつ更新できればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
わかりやすく、素晴らしいです。是非、御成敗式目が制定されるなど、武家社会700年の礎を築いた鎌倉宇津宮辻子幕府も取り上げてください!
ご視聴いただき、また格別のお言葉をいただき、ありがとうございます。他の地域の動画も面白いですよね。それも考えるのですが、鎌倉については、全く不勉強ですので、奈良や大阪など、他の地域も含めて情報を集めていき、いつか動画にしてみたいです。貴重なご意見ありがとうございます。
リアルですね
ありがとうございます。もっとこうなればというところだらけですが、少しずつ改善できればと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
上京下京の人口自体は実は平安京の頃とあまり変わらないどころか増えてるとか。
そもそも平安京は首都人口に対して無駄に広く作ってあったから、時代がくだる毎にだんだん東に密集して小さくなっていったそうな
唐の長安(9キロ×8キロ)が100万人で、平安京が10万人程度だから規模も10分の1で済む所を、4分の1(5キロ×4キロ)に設計してた。
お邪魔しました
下鴨神社からの河原町通が微妙にクネクネと曲がっているのが、昔の土手の雰囲気が有りますね。
すいません、鞍馬道か、寺町通のことですかね? 多分この時期だと河原町通はまだないような気がしますが。勘違いでしたらすいません。
六道珍皇寺の位置が八坂通り北側になっていますが、現在は松原通り北側です、移転等があったのでしょうか?調べてみましたがわかりませんでした。
いつもご視聴ありがとうございます。また、貴重なコメントありがとうございます。てっきり同じ場所だと思っていたんですが、ご指摘の通りですね。確認してみたんですが、今回ベース図として使った、新創社『京都時代MAP』の位置がここでした。江戸時代に移転したんでしょうか。何かわかりましたらお知らせしますね。
東寺は、織田信長が足利義昭を奉じて上洛してより、度々陣所として利用していたそうですね。
京の都の復興や二条御所の建設の指揮を取ったり、周囲の敵対勢力への対策の指揮を執っていたのでしょうか。
戦国時代の中頃までは東寺に対の西寺も存在していたみたいですね。
二条邸は織田信長が二条晴良から邸宅を譲り受けて整備し、二条新御所と呼ばれた三代目二条城があった所ですね。
そうなんですね。ご教示ありがとうございます。西寺は鎌倉時代には焼失して再建されなかったようですが、どうでしょうか。
@@yamajiro 『二水記』の大永7年10月27日(1527年12月7日)条に「西寺に陣を敷いた」という記録があることから、戦国時代の中期頃まで西寺は存続していたと推測できるという見解もあるようです。Wikipediaより
すばらしい
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
初コメ失礼します、貴方の旧大坂城での動画だったり聚楽第の動画だったりを見てて思った事なんですけど、今の遺構調査って文献からの推測を元にその地域を手掘りからの測量だったりしてアナログな方法で調査してる訳ですがああいった事を見ててふと気になってのが人間だったり動物だったりって定期的な健康を確認するための健康診断の時に鮮明なデータを撮るためにX線を使って検査をすると思うのですがあれをもっと巨大化して検査できる対象物の測定距離を長大化する方法って無かったりするんですかね?有るのなら遺構の調査等がかなり発展すると思いますし個人的な理想的なレベルで言うと人間を検査する時みたいに割りと鮮明に見えるレベルで見えると理想に近いですけど
仰るものに近いのは、地中レーダー探査だと思います。しかし、これは大雑把に、地下にどんな遺構があるのかをつかむものです。例えば埋もれた溝があるのかとか、古墳の埋葬施設がどのような大きさで、どのくらいの深さに存在しているのかといったことはつかめますが、100%正確かというとそうでもないですし、結局は掘らないとわからないです。あくまでも大まかな状況を把握して、今後の調査等の参考にするというものだと思います。
花の御所のすぐ隣に伊勢氏の宗家があったんですね。
そのようですね。多分もっと多くの武家屋敷があったと思いますが、いつか解明されるといいですね
近い未来もっと精巧なものが見れたりするのだろうか…
ご視聴ありがとうございます。これは個人で短期間で作ったものですので、京都市が作れば、この動画よりもはるかに正確でリアルなものが出来ると思いますよ。
京都民ですが、金閣寺という表現は観光客向けみたいで違和感がありますね
ご指摘ありがとうございます。言われてみればそうですね。金閣寺以外浮かびませんでした。鹿苑寺、なじみがない気がしますが、もし今後紹介することがあればちょっと考えてみます。ありがとうございます。
@@yamajiro京都民やけど金閣寺呼びの方が馴染んでますから別にええ思いますよ笑
@@azuki_1229_m ありがとうございます!
鴨川の水害が広かったのにおどろきました
明けましておめでとうございます。私も驚きました。常にというわけではなく、最大でということだとは思いますが、それにしても浸水する可能性があるエリアは予想以上に広かったようですね。いつもご視聴ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
平安後期の白河法皇の思い通りにならないならない物として、双六のサイコロの目、比叡山延暦寺の僧兵の強訴と並んで鴨川(賀茂川)の流れもありますからね。
田圃のど真ん中にあったんだな...
今回はある程度周辺の集落を追加したのですが、多分もう少しあったと思います。またわかれば追加していこうと思います。
@
ありがとうございます。
いきなりの自分語り失礼しますが、応仁の乱で京都を破壊したのは私の先祖です。大内政弘、山名宗全です。600年前のおじいちゃん達の悪事の結果を見るのは不思議な感じです。
我が家の蔵が焼けたこの前の戦争は太平洋戦争でなく1160年の平治の乱のこと、というのは一寸、無理があるというか京都ジョークなのかなと。
いつもご視聴ありがとうございます。そうなんですね。それは初めて聞きました。私も昔、司馬遼太郎?が新聞記者の時に取材した古老が、「あの戦争の時は大変だった。」と聞いた時、太平洋戦争のことだと思ったら鳥羽伏見の戦いだったというのを読んだ気がします。当時大笑いしましたが、よく考えたらこれが成り立つのは結構難しい気がして、戦後間もなくの話で、90歳以上の高齢者で、7~8歳の時の記憶ならギリギリ成立しますが、どうなんでしょうね?
こんにちは。
こんにちは!今年も来ましたね(笑)。よろしくお願いいたします。
私は八坂神社の創建は、応天門の変(866年)で失脚した伴大納言や紀氏の怨霊を鎮める為に建立されたと考えています。八坂神社創建は869年と876年が伝わつていますが、868年配流先の伊豆で伴大納言は亡くなってをり、政敵であった左大臣源信もその直後に死亡。又876年4月10日は大内裏が三日三晩不審火で全焼しており、10年前の866年4月10日の応天門の不審火との関連を心配した朝廷はこの年伴大納言の孫の罪をとき、都に戻しています。
なるほど。怨霊を鎮める目的もあったかもしれませんね。詳細な情報ありがとうございます。
これじゃあ上洛したくとも上洛できないよね、誰にどう礼をすりゃいいやら。
三好『こっちですよ💕案内料頂きます💕』
ひっでえ商売しはりまんなあ🗿
代わりに作った私が案内します(笑)。
城郭都市だったのか。
当時の特殊な状況で成立した街の姿だったかもしれませんね。
AIナレーターの声は種類が少ない印象。
私は気に入っているんですが、なんか怪しい広告の声としてよく聞く気がします(笑)。
六波羅蜜寺
中世のあの辺りだいぶ治安悪いけど現存してるってすごい()
お詳しいですね。もう少しこの辺りの街並みについて再現できればと思ったのですが、資料がなくて出来ませんでした。また何か本などご存じでしたらお知らせください。
奈良時代って都の移転が多かったのはトイレ(便所)の事情ではないかな?処理する流通が解らない
あとは体を清潔にするお風呂屋もね 最初は男女共用だたのだろうね 水とか燃料を考量するとや燃えないと思うし夫婦という固定概念がなかったようにも思える 戦前までは神社は男女の出会い場でもあったからです
都の移転には、政治的・宗教的な理由が大きかったのではないでしょうか。風呂は、当時はまだサウナ風呂のようなもので、現在の銭湯のようになるのは江戸時代中期以降のようです。
昔の京都(首都)ってこんなに殺風景だったんですか?
とりあえず入手できた資料を基に作りましたが、上京と下京については、極端に誓っているという事はないと思います。ただ、資料不足で作れませんでしたが東山を含めて、周辺の集落や社寺はもっとあったと思いますので、次回以降、わかったことを反映させて行きますので、またご覧ください
法堂はほっとうでなくはっとうでは?
西だけに堀があったのは誰に備えていたのか
ご教示ありがとうございます。東側にないのは本当に謎ですよね。
@yamajiro 曹洞宗だとそう読むだけで他の宗派は違うかもしれないので悪しからず……
東側は信頼できる武将勢力とかだったんですかね
@@anchira ご丁寧にありがとうございます。妙心寺のサイトでも「はっとう」となっていましたので、禅宗全般ですかね? 東側については、私も京都市の方にお聞きしたんですが、鴨川があるから、相国寺があるからという理由でなかったのではとのことでした。ちょっとよくわかりませんね。西側からの襲撃に備えていたのか、だとしても回り込まれたら意味がないですし。謎ですね。
金閣寺はどうなっていたですの?
ポツンとあったですの?
よくお気づきになりましたね! 金閣寺だけそれっぽく作ったんですが、この時期金閣寺以外の建物がどうなっていたのか、わからなかったので、これ以上作らず保留していたら時間切れになってしまいました(わからないのは他の寺社もそうなんですけどね)。これからも追加していくつもりですので、わかることがあれば追加しようと思います。
うう…。見たいのにナレーションの声が気持ち悪すぎて5秒でリタイア。お願いだから普通の声で話をしてください。😢
すいません、この声でずっとやってきていますし、こういった意見はほとんどないので、今のところ変える予定はないです。
@@yamajiroそうですか、残念です…。字幕を付けるのはどうでしょうか?それなら音オフで視聴できるので。
これで平安京エイリアンをやりたい
ありがとうございます。やれそうだといいんですがクオリティが・・。