Three preludes BWV 1007, 999, 846 by J.S Bach│Guitar by masanobu NISIGAKI│Commentary performe
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 10 พ.ย. 2020
- ~For children and beginners, amateurs who learn music with me~
Commentary performe and transcription by Masanobu NISIGAKI
▶Bach’s other profile
Three preludes BWV 1007 for cello/999 for lute /846 for clavier, mainly BWV1007
▶Performe start at 16:37
▶Performance : Masanobu NISIGAKI. Japan
・Valotti temperament:A = 430
・Instrument:Coffe Coguette (1830 Mirecourt,France)
#masanobuNISIGAKI
#Bach
#Prelude - เพลง




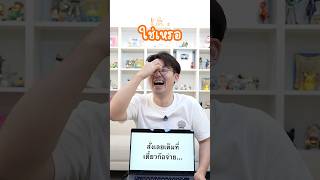




西垣の自己ツッコミです。BWV999 小前奏曲 で偽終止ともうしてますが、
ここではもちろんそれそのもののためでつかわれているのではなく、バッハは混沌にはいる
偽終止の行く先かわりにこの複合和音を使う、と言う意味です。
六度音のうえにサブドミナントを乗せることを大事な箇所で多用します。もちろんサブドミナントの七ではなくて六度和音の複合です。
この場合はそれをプラガルの代わりにつかわれて下降導音を意識しています。
では、次の小節の和音はなにか? というと下降導音の固執低音上に乗っかっている、と感じられます。全部を楽譜にすると超複調の瞬間があらわれます。
全体は属音上の短調で展開されるので、属和音の調はⅡ度音上の長調となります。
それが属音上の短調で広がるのですが、冒頭に暗示されているようにピカルディの解決
に向かいます。これは当時自然なことです。前奏曲という性格上短調であってもピカルディなどで長調の終止が必要だったのです。このことはバッハがピカルディの終止に拘らなくなった1715年以降もあまり変わりません。なぜなら、続くべき曲から見ると前奏曲そのものが、属調への大きな旅だからです。だから前奏曲というのは単独で演奏されるさいも続くべき世界を暗示しなくてはならない、と思います。ショパンであってもドビュッシーのあの曲でも・・こんなことは知らなくとも美しい演奏は充分できるはずだし、ぼくの言葉の能力では終わりそうにないので、説明不足でした。いわゆる「平均律クラビア」とその表紙ページについては小中学生にもわかるような解説をした原稿を書いたと・・あったはず・・探しておきます。
柔らかく優しい音
自己つっこみ その2 感染以降 ネットをよく使うようになって多く質問をうけることの返信を兼ねて。 いわゆる平均律クラビアの呼称に問題かな? と語るのか。今回もつかったそのタイトルページの謎の図形の説明を中学生むき(小学校高学年対象のつもりで書いた)の記事を置いておきます。
ぼくは古典音律を使うけれどもけっして平均律を否定するものではありません。よい演奏ができればなんでもよいのです。古典音律でも 浅学で友人の製作家平山さんに教えてもらうまでしらなかったナイトハルトなどはほぼ平均律と共存可能、でも古典の性格もかすかにある。ヨーロッパの古いタイプの調律師はほぼヤングを「平均律」として調律している現場も目撃しました。ま・・なんでもよいのです・・ただ和声学は古典音律をしらないとわからない部分もあります。
www.koube.jp/public/onritu.pdf